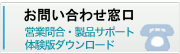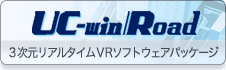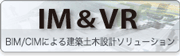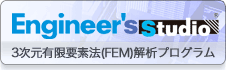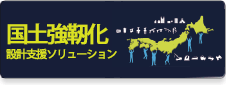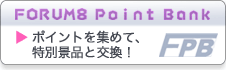|
前回は、ブロック面情報がない面と面の結合法について、結合する要素同士の構成節点回りが揃っていないと結合することができないことを説明しました。
今回は、要素の構成節点回りをそろえる操作を行ってからブロック面情報がない場合の結合法を実行します。(モデルについては前号のサポートトピックスをご覧ください)。
例:要素構成節点回りをそろえる
構成節点回りをそろえる方法は複数ありますが、今回は基準軸を指定してその基準軸に第1辺をそろえる操作を行います。【変更】メニューの中から【構成節点】‐【基準位置】を選択します。 |
|
|
対象「2次元要素-第1辺基準軸」、基準軸「スクリーン」、指定方法「構造物全体」を指定して「OK」をクリックします。画面上から下記の2節点を指定して基準軸を決定します。
全ての要素の構成節点開始位置(第1辺)が統一されました。
ブロック面情報がない場合の面と面の結合
構成節点回りがそろったので、再度、面と面の結合を行います。【生成】メニューから【結合】−【2次元ブロック】を選択します。
生成節点数に結合間の節点数(=3)を入力して「OK」をクリックします。
画面上より次の順序で結合の指定を行います。
- 結合する1番目のブロックを選択します。1番目のブロック内の、基準とする要素を1つ選択します。
- 結合する2番目のブロックを選択します。
- 2番目のブロック内の、1番目のブロックで指定した基準とする要素と対応する要素を選択します。
画面で確認
線画描画で、ツールバーの描画ボタンメニューから「ブロック図」を選択します。図より作業用に作成した1次元ブロックだけが表示され、3次元ブロックのサイドは表示されません。このことから作成された3次元ブロックは単純ブロックであることがわかります。
結合法(面と面の結合)のまとめ
ブロック面情報があるブロック面同士の結合は今回紹介したような操作が不要なため簡単に結合することができます。その反面、1ブロック面ごとの結合になるので自由度は低くなります。2次元ブロック同士の結合は構成節点回りに注意すれば複数の2次元ブロックを一括で結合できるなど自由度が高いというメリットはあります。それぞれの特徴を理解して使い分けることをお勧めします。
次回は4つのブロック生成コマンド最後のコピー法を説明します。
|