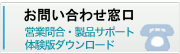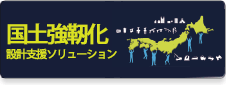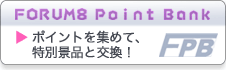|
常日頃は誰も意識しないことだが、スポーツには不思議なことが山ほど存在する。たとえばサッカー。そもそもサッカーとはどういう意味か?フットボールならFoot(足)ball(球)で何となくわかる。が、サッカーは意味不明。
おまけにサッカーはなぜ手でボールを扱ってはいけないのか?それを考えるには、紀元前2千年以上昔の古代メソポタミアの世界まで遡る必要がある。
チグリス・ユーフラテス両大河に囲まれた古代メソポタミア地方はきわめて肥沃で、その豊饒な土地を巡って民族の興亡が相次いだ。そこで「丸いモノ」を奪い合う遊びが生まれた。「丸いモノ」は地上には存在せず、空に輝く太陽の象徴として、「丸いモノ」を奪い合う遊びは、太陽を支配し、地上の世界の支配者を決める遊びとして発展した。
メソポタミアで(丸い)頭蓋骨などを奪い合っていた遊びは、古代ローマ帝国に伝わり、動物の皮袋に石や布などを詰め込んで縫い合わせた「丸いモノ」を、2組に分かれた男たちが奪い合うカルチョという球戯に発展する。イタリア語では今もサッカーのことをカルチョと呼び、トトカルチョ(サッカーくじ)という言葉も生んだ。
カルチョが中世フランスに伝わりラ・シュール(La Soule)という遊びに発展する。これはクリスマスや復活祭などの宗教的記念日に、村中をあげて「丸いモノ」を奪い合った遊びで、聖職者も貴族も騎士も農民も、身分を超えて千人以上の村人が2組に分かれ、村はずれにある教会や大木など、ゴール(目的地)と決めた場所へ運ぶのを競った。
そのとき用いられた「丸いモノ」は、豚や牛の膀胱を膨らませて作られた。遊びの最中にそれが破れると、すぐさま豚や牛を殺して膀胱を取り出し、中を洗って穴を紐で縛り、群衆の中に投げ入れたというから、かなり血の気の多い遊びで、実際大勢の負傷者や死者まで出たという。
豚や牛の膀胱で作られた「丸いモノ」は、けっこう重いうえに血や脂肪で滑りやすく、手で掴んで投げるより、蹴ったり棒で叩いたりしたほうが扱いやすく、遠くへ飛ばすこともできた。そんな遊びがイギリスへも伝わり、村や町をあげて、マス(群衆)フットボール、ストリート(街中)フットボール、モブ(暴民)フットボールなどと呼ばれる大騒動の遊びに発展。19世紀初頭の産業革命の頃に工場用地として農地を奪われた農民たちは不満をぶつけ、何日間もフットボールに明け暮れた。
じつはサウスポーとは、ナイター設備のない時代に、西日が右打者の目に入らないよう、「本塁から二塁方向は東北東を理想とする」と野球場の方角がルールで定められ、左投手の手pawが南southから出てきたためsouthpawという言葉が左利き投手のこととなったのだ。
その一方でオックスフォードやケンブリッジの大学やパブリック・スクールの校庭でもゴールを定めて行われるようになり、ルールの統一と制定が進み、足だけを使うフットボールを行う連中がフットボール・アソシエーション(協会)を設立。そこで行われた手を使わないフットボールがアソシエーション・フットボール(Association
Football)と呼ばれるようになり、それが、Assoc Football(アソック・フットボール)→Asoccer(アソッカー)→Soccer(サッカー)と略されたのだ。
だから明治時代初期にフットボールが日本に伝えられたとき、サッカーは「ア式蹴球」と翻訳され、いち早く取り入れた慶應大学には、今も部活動に「ア式蹴球」「ラ式蹴球(ラグビーフットボール)」という名称が残っている。
古代メソポタミアから西洋に広がった「太陽の奪い合い」は東洋へも広がり、中国を経て日本の飛鳥時代には「擲毬〔くゆるまり〕」と呼ばれ、中臣鎌足と中大兄皇子が「擲毬」の最中に蘇我入鹿の暗殺(乙巳の変=大化の改新)の密談を交わしたことが『日本書紀』にも書かれている。
つまりサッカーというスポーツを語れば、世界史や日本史を語ることにもつながり、そのような「知的作業(知育)」を含むスポーツは「体育(身体を鍛える教育)」だけで語られるべきではないのだ。
|