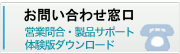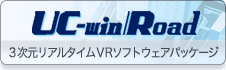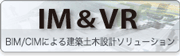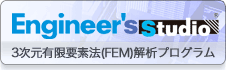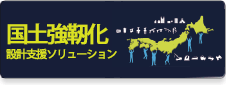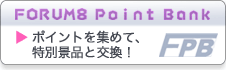| �`�Q�|�P�D |
���n�Ղ̔���`���l�����Ȃ��ꍇ
�@�@�@�Y�̕ψʂɂ�炸�A�n�Ք��͌W�������Ƃ���ݒ肪�s���Ă���ꍇ�́A���̂܂�kh=kho�̒l���g�p����܂��B
���n�Ղ̔���`���l������ꍇ
�@�@�Echang�̎�����ђe������͂藝�_�ɂ����(�d�����@�ȊO�̏ꍇ)
�@�@�@�Y���n�Ք��͂ɒB�����ꍇ�́A���L���Œn�Ք��͌W�����Z�肵�܂��B
�@�@�@�@kh = Py�E��-1
�@�@�E�d�����@�̏ꍇ
�@�@�@�@�Y���n�Ք��͂ɒB���������̒n�Ք��͌W���́A0�Ƃ��Čv�Z���܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�Q�D |
�y�̍Y�̗l�ɍY�z�u���l���������͂̕��z�͂ł��Ȃ��̂ł��傤���H |
| �`�Q�|�Q�D |
�y�̍Y�̗l�Ƀt�[�`���O���S�̎��́A�Ȃ����[�����g����t�[�`���O�̉�]���l�����Ċe�Y�̎��͂��Z�肷��悤�ȋ@�\�͂���܂���B
���͂̎w��́A�x�_�P�ʂōs���܂��B
���o�[�W�����ł́A�x�_���ł̍Y�̏ڍׂȔz�u�����܂���B
���͂́A�z�u�{���ɂ��ϓ��ɕ��z����܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�R�D |
�Y���n�Ք��͂��l�����Ȃ��v�Z�͉\�� |
| �`�Q�|�R�D |
�\�ł��B
Ver4.0.1�ɂāu�����͂̌����v�ɂ�����n�Ք��͌W���̎Z�莞�ɑY���n�Ք��͂��l�����Ȃ��ݒ��lj����܂����B�u�v�Z�����b�����͌����b��͏����v��ʂɂĐݒ肵�܂��B
���̐ݒ���s���Ă���ꍇ�́A�Y���n�Ք��͂ɒB���Ă��n�Ղ˂�0.0�Ƃ͂����A���̂܂ܕψʂɂ��ጸ���s���v�Z���܂��B
���Achang�̎���K�p����ꍇ�́A�ݒ�ɂ�炸�Y���n�Ք��͂ɒB���Ă��n�Ճo�l��0.0�Ƃ��邱�Ƃ͂���܂���B |
| �@ |
|
�p�Q�|�S�D |
�n�Ք��͌W�����w�肳�ꂽ�Y�ψʂ܂ł́A���Ƃ���悤�Ȍv�Z���ł��܂����H |
| �`�Q�|�S�D |
�\�ł��B
�n�Ք��͂̌W�������Ƃ���Y�����ψʂ͈̔͂��w�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�͈̓����w�肳�ꂽ�ꍇ
(0.0�� y �������͒l)�͈̔͂����ƂȂ�܂��B
kh =�ȁEkho �@��=1/�ヿ
(���� y)�@kh = kho�Ey�O(-1/2)
y�F�������������ψ�(�����ψʂ�cm�ŕ\���������ł̖���������) |
| �@ |
|
�p�Q�|�T�D |
�n�Ք��͌W�����Z�肷�郿Eo�̃��̒l���y�Ƒ傫���قȂ�܂����A�Ⴄ���̂Ȃ̂ł��傤���H |
| �`�Q�|�T�D |
�y�ƌ��z�ł́A�n�Ք��͌W���̎Z�莮���قȂ�A���ɂ��Ă��Ⴄ���̂ł��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�U�D |
�����͌����ɂ�����Y�������o�l�iK�l�j�̎Z�o�͂ǂ̂悤�ɋ��߂Ă��܂����H |
| �`�Q�|�U�D |
�w���v�́u�v�Z���_�y�яƍ��̕��@�v�|�u������R�͂̌����v�����Q�Ƃ��������B
�����́u�����͂̕��z���@�v�ɋL�ڂ��Ă���܂��Ƃ���A�����u���b�N���̍Y�̍Y�������ψʂ�����ƂȂ�悤�ɁA�e�Y�̍Y�������o�l���Z�o���Ă��܂��B
1�{�Y��e���x����̂͂�Ƃ��ă��f�����A�Y���ɒP�ʐ����dHoi���ډׂ��A�Y���ɐ����鐅���ψʃ�oi�����߁AKi��Hoi�^��oi �ɂ��Z�o���Ă��܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�V�D |
�|�ǍY�̐����͌����ɂ����āA���e�Ȃ������͍ő�Nmax�������͍ŏ�Nmin�̕����傫���Ȃ��Ă���̂͂ǂ����Ăł����H |
| �`�Q�|�V�D |
���e�Ȃ����[�����g�̎Z�莮�́A�w���v�u�v�Z���_�y�яƍ��̕��@�b���e�Ȃ����[�����g�b���|�ǍY�v�ɋL�ڂ̂Ƃ���ł��B
�|�ǍY�̏ꍇ�́A����0�t�߂��s�[�N�̎O�p�`���z�ƂȂ�܂��̂Ŏ��͈͂̔͂����ł���A���͂��������������e�l���傫���Ȃ�܂��B
���̋��e�Ȃ����[�����g�Ǝ��͂̊W�́AM-N�}�ł��m�F���������ł��܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�W�D |
�ꏊ�ł��Y�Ŏ�S�̍ގ���ύX���Ă����e�Ȃ����[�����g�̒l�ɉe�����Ȃ��̂͂Ȃ��ł����H
�S�،a��ύX����ƒl���ς��܂��B |
| �`�Q�|�W�D |
���e�Ȃ����[�����g�́A���L���r���������l�Ƃ��܂��B
�@Mrc�F�R���N���[�g���k�����͓x���R���N���[�g�̋��e���k���͓x�ɒB����Ȃ����[�����g
�@Mrs�F�ŊO���S�̉��͓x���S�̋��e�������͓x�ɒB����Ȃ����[�����g
�S�̍ގ���ύX���Ă��A���e�Ȃ����[�����g�̐��l���ς��Ȃ��ꍇ�́A����������e�Ȃ����[�����g���R���N���[�g���猈�肳��Ă��邽�߂ł��B
Mrc���Z�肷��ꍇ�A�S���R���N���[�g���Z���čl�������̂ŁA�R���N���[�g���狖�e�l�����܂�ꍇ���S�،a���ύX�ɂȂ�ƒl���ς��܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�X�D |
�|�ǂ̔��a��̒ጸ�W�����I�ǎ����l������Ƃ����ꍇ��Mu�̒l���ς��Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���H |
| �`�Q�|�X�D |
����1113���̋K��ɂ��ጸ�́A���e���͓x�ɑ��Ă̋L�q�Ȃ̂ŁA��y�ɑ��Ă͒ጸ���s���Ă���܂���B
�u���z��b�\���v�w�j�vP304��Mu�̎Z�莮���L�ڂ���Ă��܂����A������ł���y��ጸ����L�q�͂������܂���B�O�y�[�W�̏I�ǎ��̈��k�ϗ͎Z�莞�ɂ͍l�����Ă��܂��B
�܂��A�|�ǍY�̃T���v���f�[�^���쐬����ۂɎQ�l�Ƃ��܂����u�킩��₷����b�̐v�ƌv�Z��(�����y�،�����)�v�ɋL�ڂ����v��ɂ����Ă�Mu�Z�莞�̃�d�i���̐v��ł̓�d�F�I�nj��E���̐v�p���E���x��p���܂��j�̓�d=1.1�EF(�v����x)�Ƃ��Ēጸ�͍l������Ă��܂���B
��L�������Q�l�Ɍ��o�[�W�����ł́AM-�ӎZ�莞�ɂ͔��a��̒ጸ���l�����Ă���܂���B |
| �@ |
|
�p�Q�|�P�O�D |
���w�n�ՂƂ����ꍇ�A�Ȃ����[�����g���͂ǂ̂悤�ɎZ�肳���̂ł��傤���H
�o�͂Ŏ������m�F���邱�Ƃ��o���܂����H |
| �`�Q�|�P�O�D |
���w�n�ՁA��l�n�Ղ�chang���I������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ��ẮA�e������̉��i�����}�g���N�X��p������@�j���K�p����܂��B
�P���Ȏ��ł͂Ȃ����߁A���̏o�͂͂���܂���B
��@�ɂ��ẮA��ʓI�ȍ\���͊w�̌����W�ȂǂɋL�ڂ���Ă���܂��̂ł���������Q�Ƃ��������܂��悤���肢�v���܂��B
���Џ��L�̎����ł́A���L�ɋL�ڂ��������܂��B
�u�\���͊w�����W (�y�؊w��)�vP173�`
�u�����R���N���[�g�Y ��b�\���v�}�j���A�� ���z�� 2009�N5���v(�Вc�@�l �R���N���[�g�p�C�����Z�p����) P261�` |
| �@ |
|
�p�Q�|�P�P�D |
�Y�̏d�ʂ͂ǂ̌v�Z�ɉe������̂ł��傤���H |
| �`�Q�|�P�P�D |
���e���������͂̎Z��Ɏg�p���܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�P�Q�D |
�Y�̂̋��e�ϗ͂��Z�肷��Ƃ��̒����a��ɂ��ጸ�͉��ɋL�ڂ������̂ł��傤�� |
| �`�Q�|�P�Q�D |
�ʒB�i���a59�Z�w��392�j�ɂ��܂��B |
| �@ |
|
�p�Q�|�P�R�D |
�t�̉e���́A���e�x���͎Z��ɍl������܂����H |
| �`�Q�|�P�R�D |
�����ł͍l������܂���B
�t�w�̎��ʖ��C������ꍇ�́A�u�n�w(�o�^)�b���w�n�Ձv�̐ݒ�ɂāA�t�w�̎��ʖ��C���l�����Ȃ��悤�ݒ肵�ĉ������B
�t�ɂ����ʖ��C�̒ጸ�ɂ͑Ή����Ă���܂���B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�P�S�D |
��b�w�j2019�N��b�w�j��I�����APRC�Y�̌v�Z���s�����Ƃ���N-M�}�̃��C����PHC�Y�Ɠ����`��ɂȂ邪�A�������̂ł��傤���H |
| �`�Q�|�P�S�D |
2019�N�w�j��I������Ă���ꍇ�A��b�w�j(2019)P280�̋L�q�ɂ��PRC�̋��e�Ȃ����[�����g��RC��b���ގw�j5.2.2PRC�Y(P220�`)�̋L�ڂɏ������ĎZ�肵�܂��B
����PHC�Y�Ɠ����Ȃ̂ŁAN-M���C���̌`��͓����ƂȂ�܂����A�S���l�������̂ŋ��e�l�͈قȂ�܂��B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�P�T�D |
�P�Y���˃��f�����w�肵���ۂɒn�Ճ��f���Ƃ��āu�������f���v�u�����@���f���v��2�p�^�[��������ƋL�ڂ�����܂����A�I������X�C�b�`����������܂���B�P�Y���˃��f���A���w�n�ՁA����`�˂�I�������ۂɂ́A�ǂ���Ōv�Z����Ă���̂ł��傤�� |
| �`�Q�|�P�T�D |
�n�Ղ̔���`���l������ꍇ�A�P���ȃP�[�X�i�����͂̕��S��������ȃP�[�X�j�ł́A�����@�ɂ�����`���l�����܂��B
���L�̃P�[�X�ł́A�����@�ɂ�����`���l�����܂��B
�@�E�Y�̂̔���`���l������ꍇ
�@�E�n�Ղ̔���`���l�����A���A�����͂̕��S���s�ϓ��̏ꍇ
�n�Ղ̔���`���l������ꍇ�ł��A�n�ՂƍY�̑g�������l�������^�C�v���P��ނ����Ȃ��ꍇ�A�S�Ă̍Y�͓��������i�����͂̕��S���ϓ��j�ƂȂ�܂��B
���̂悤�ȃP�[�X�́u�����@�v���K�p����܂��B
�Y�̂̔���`���l������ꍇ�A�n�Ղ̔���`���l������ꍇ�i�����͕��S���s�ϓ��j�́A�Y���̌��ʂ��݂��Ɋ��������ĕς���Ă����̂Ōv�Z�����G�ƂȂ�u�����@�v�ł͎����ł��Ȃ��P�[�X���z�肳��܂��B
���ׁ̈A�u�����@�v�͒P���ȃP�[�X�ɂ̂����č̗p���Ă��܂��B
�����ɂ���Ď����Ōv�Z���@���K�p����邽�ߑI���͂������܂���B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�P�U�D |
�����ψʖ@�̉�͂Œn�Օψʂ̉e���́A�ǂ̂悤�ɍl�������̂ł��傤���B |
| �`�Q�|�P�U�D |
�Y�̐ߓ_�ɋ����ψʂƂ��č�p�����܂��B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�P�V�D |
�p�C���L���b�v�d�ʂ͂ǂ̂悤�ɎZ�肷��̂ł��傤���B�ǂ̐ݒ肪�e�����܂����B |
| �`�Q�|�P�V�D |
���L���ŎZ�肵�܂��B
�p�C���L���b�v�d�� = A*h*��
A�F�p�C���L���b�v�ʐ�
h�F�p�C���L���b�v����h �u�Y�z�u�b�p�C���L���b�v�`��|h�v�œ��͂��ꂽ�l
���F�P�ʑ̐Ϗd�ʁ@�u�ގ��b�R���N���[�g�i��b�X���u�j�b�P�ʏd�ʁv�œ��͂��ꂽ�l
|
| �@ |
|
�p�Q�|�P�W�D |
�d�����@�ɂ��āA�Z�����͂���яI�ǎ��͂ɂ��M-�ӂ�ݒ肵�܂����A�d�𑝂₵�čs���ߒ���M-�ӂ͕ς�邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ��������ł悢�ł��傤���B |
| �`�Q�|�P�W�D |
���l���̒ʂ�ł��B�v�Z����M-�ӊW�͈��ŕς��܂���B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�P�X�D |
�|�ǍY�̋Ǖ��������l�������ጸ�W���̎Z��ɂ����āA���a���͕��H����l������ׂ��Ȃ̂ł��傤���B
���z��b�\���v�w�j�i2001�N�j�⍐��1113�������Ă����H����������Y�̗̂L�����a�ƂȂ��A�h�|�ǍY�̔��a�h�Ƃ����L�ڂ���Ă��܂���B |
| �`�Q�|�P�X�D |
���L�A���{���z�w��̏��Ђɂ����ẮA���a�͕��H��������L�����a��p���Ă��܂��B
�������ό`����A���a��p���Ă��܂��������̎��ł��B
�E���K�͌��z����b�v�w�j
�E��b���ނ̋��x�ƕό`���\�@��
�ʐς�Y���ɍl�����A���a�ɂ������H������l�����Ȃ��̂͐��������Ă��炸�A���H������l����������������ƍl���܂��B
�E���K�͌��z�\������b�v�w�j
�E���K�͌��z����b�v��W
�ɋL�ڂ����|�ǍY�̐v��ł́A����������a�ɕ��H������l�����Ă���܂��B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�Q�O�D |
�u�Y�̒f�ʕω��ʒu�v�ł��u�w���v�ł��Ȃ��̂ɔS���y�n�Ղ����������ʒu������̂͂Ȃ��ł��傤���B |
| �`�Q�|�Q�O�D |
�S���y�̑Y���n�Ք��͓x�̎Z�莮�́A��/B(�Y�a)��2.5�����ɕς��܂��B
���ׁ̈A�Y�a�~2.5���̈ʒu�ŕ������Ă��܂��B
���̏ꍇ�̐[�x�́A�n�\�ʂ���ł͂Ȃ��A�Y�̐v�n��Ֆʂ���̋����Ƃ��Ă��܂��B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�Q�P�D |
�������S�������Ȃ�A��͕��@��ύX���Ă��������ʂ������܂����B |
| �`�Q�|�Q�P�D |
��͕��@���قȂ�ꍇ�́A��̓��f�����قȂ�܂��̂Ō��ʂ͋ߎ����܂����A���S�ɂ͈�v���܂���B
�Ⴆ�A���z�˂Ƃ���ꍇ�Ɨ��U�˂̈Ⴂ�ł���̍��͐����܂��B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�Q�Q�D |
PHC�Y�̋��e�Ȃ��������͓x�͂ǂ̌v�Z�ɉe������̂ł��傤���B |
| �`�Q�|�Q�Q�D |
�Y�̂̈������e�ϗ͎Z��ɍގ���ʂɂĐݒ肳��Ă���u���e�Ȃ��������͓x�v�̒l���g�p���܂��B
�w���v�u�v�Z���_����яƍ��̕��@�b2001��b�w�j�b�x���͂̌����v(1)�Y�̋��e�̗͎Z����@�@�������������@PHC�Y�����Q�Ɖ������B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�Q�R�D |
�n�Ղ̕ψʂ��l������ꍇ�A�Y��[�ʒu�̕ψʂ�0.0�Ƃ��Ĉ����܂��B
�����W���������ɒn�Ղ̕ψʂ��l�����邱�Ƃ��ł��܂����H |
| �`�Q�|�Q�R�D |
�u�v�Z�����b�����͌����b���ʁv��ʁu�n�Օψʁv�̑I�����u�Y��[�ʒu����̑��Εψʁv���I������Ă���ꍇ�́A�Y��[�̕ψʂ�0�Ƃ������Εψʂ�p���܂��B
������̐ݒ���u�H�w�I��Ղ���̐�Εψʁv�Ƃ���ƍY���ɂ�����炸�����ʒu�ɂ͓����ψʂ��K�p����܂��B
|
| �@ |
|
�p�Q�|�Q�S�D |
2019�N�w�j�����Ƃ��āA�����͌������s�����ꍇ�Ɏ��������͂̔��肪�s���܂����A����͉��ɂ����̂ł��傤���B |
| �`�Q�|�Q�S�D |
�u��b���ނ̋��x�ƕό`���\(���{���z�w��)�v�ɂ����ẮA�u�\�������ɂ�茟���ꂽ����(���͔�)��K�p�͈͂Ƃ��邱�ƂL�����B(P39)�v�ƋL�ڂ���Ă���A���E�l�Z��ɂ����鎲�������͈͂̔͂��Y�했�ɒ�߂��Ă��܂��B
��L�K��Ɋ�Â��A�f�ڂ���鎲�������͔�͈͔̔�������{���Ă��܂��B
|
|
�@ |
|
�p�Q�|�Q�T�D |
PRC�Y�̖��ؕ����́APHC�Y�Ƃ��Ĉ�����̂ł��傤���B |
| �`�Q�|�Q�T�D |
�ݒ�ɂ�PRC�Y�Ƃ��Čv�Z����̂�PHC�Y�Ƃ��Čv�Z����̂���I���ł��܂��B
�܂��APHC�Y����K�p����ꍇ�A�ጸ�W���A�����W���A�����͈͂̔͂ɂ��Ă�PHC�Y�̐ݒ��K�p���邩�ۂ�I���ł��܂��B
���������A�Ȃ��ɂ��ẮA�I���ɂ�炸�S���l�����Ȃ������ɂ��Ă�PHC�Y�Ɠ��������ɂȂ�܂��B
|
|
�@ |
|
�p�Q�|�Q�U�D |
��b�w�j2019�N��I�����n�Ղɑ��鋖�e�x���͂̎Z������b�w�j�ɂ��Čv�Z���s�������Y��[�nj����ł�0�ƂȂ��Ă��܂��܂��B
�ǂ̂悤�Ƀł����߂Ă��܂����H |
| �`�Q�|�Q�U�D |
�Y��[�nj����ł�2019�N�� ���z��b�\���v�w�j �\6.3���ȉ��̕��@�ŋ��߂܂��B
- ��]�ѓ��Y�F�[�Y��1.0�A�J�[�Y��0.8
- �ō��ݍY �F�[�Y��1.0�A�J�[�Y�ł͈ȉ��̎��ŋ��߂�
�@2��(LB/dI)��5�̏ꍇ�@��=0.16 (LB/dI)
�@5��(LB/dI)�̏ꍇ ��=0.8
�����ɁA
�@LB�F�x���w�ւ̍����꒷��(m)���u�n�w��ʁb�n�Ֆʁv�Őݒ肵���x���n�Ֆʁ`�Y��[�܂ł̋������g�p���܂��B
�@dI �F�Y�̓��a(m)
�������A�u�n�w��ʁb�n�Ֆʃ^�u�v���x���n�Ֆʂ̃`�F�b�N���O��Ă���ꍇ�͍����꒷�Ȃ��ƂȂ�Ł�0�ƂȂ�܂��B
|