ACCS HP https://www2.accsjp.or.jp/
ACCS(一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会は、デジタル著作物の権利保護や著作権に関する啓発・普及活動を通じて、コンピュータ社会における文化の発展に寄与しています。オービックビジネスコンサルタント(業務ソフトウェア開発・販売)の創業者・代表取締役社長 和田成史氏が理事長を務め、多数のソフトウェア開発企業が会員として所属。フォーラムエイトも、同協会の活動に賛同して2022年に入会し、ソフトウェアの地位向上のため活動を継続しています。
近年、生成AIのビジネス活用が急速に進んでいます。2023年10月には、テレビCMに「AIタレント」が登場し、大きな話題となりました。一方で、2024年3月、海上保安庁が生成AIを利用して作成したパンフレットを公開したところ、著作権や倫理に関する批判が殺到し、公開を中止するトラブルが発生しました。このような事例から、生成AIの活用に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本稿では、生成AIの活用と著作権に関する基本的な考え方や注意点を解説いたします。
AI(人工知能)とは、コンピュータが人間のように考える・学ぶ技術の総称です。たとえば、音声認識や画像認識、データ分析など、特定のタスクを自動化する技術がこれにあたります。一方、生成AIは、AIの一種で、文章や画像、音楽などのコンテンツを自動的に作り出す技術を指します。生成AIの代表例としては、ChatGPTなどの文章生成ツールやStable Diffusionなどの画像生成ツールが挙げられます。これらのツールはビジネスでは文章作成やデザイン案の生成に使われています。
生成AIと著作権の問題については、2024年3月に文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会から「AIと著作権に関する考え方」が公表されています。詳細は本資料をご覧いただきたいですが、ここではその基本的な考え方を紹介します。
AIと著作権に関する考え方について
文化審議会著作権分科会法制度小委員会(令和6年3月15日)
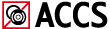
- この文書(「本考え方」)は、生成 AI と著作権に関する考え方を整理し、周知すべく、文化審議会著作権分科会法制度小委員会において取りまとめられたものである。
- 本考え方は、その公表時点における、本小委員会としての一定の考え方を示すものであり、本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成 AI やこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではないことに留意する必要がある。
- 今後も、著作権侵害等に関する判例・裁判例をはじめとした具体的な事例の蓄積、AI やこれに関連する技術の発展、諸外国における検討状況の進展等が予想されることから、引き続き情報の把握・収集に努め、必要に応じて本考え方の見直し等の必要な検討を行っていくことを予定している。
生成AIと著作権の問題は、大きく分けて「開発・学習段階」と「生成・利用段階」の2つに分けて考える必要があります。
まず、開発・学習段階では、日本国内の場合、著作権法第30条の4が適用されます。この条文の要件を満たせば、著作権者の許諾を得ずに、著作物を学習用データとして収集・複製し、データセットを作成してAIを開発することが可能です。ただし、著作権者の利益を不当に害するような利用は認められません。また、画風を模倣する学習は許されますが、特定の絵柄(表現)を意図的に出力させるための学習は著作権侵害となる可能性があります。
次に、生成・利用段階です。本稿の読者の多くは、生成AIを利用する立場にあるかと思います。生成AIを利用して作成したコンテンツは、AIを使わずに作成したものと同じように、著作権侵害にあたるかが判断されます。たとえば、生成AIを使って他人が著作権を持つキャラクターのイラストや文章をそのまま出力し、ビジネスで利用すれば、引用などの権利制限規定が適用されない限り、著作権侵害となります。
つまり、「生成AIの利用=著作権侵害」ではなく、「生成AIを使って他人の著作物を無断で利用することが著作権侵害になる」という点を理解しておきましょう。
生成AIをビジネスで活用する際、「生成AIで作った作品が著作権で保護されるのか」という点も気になるでしょう。この点について、「AIと著作権に関する考え方」では、生成AIの利用者がどの程度「創作的寄与」をしたかで判断されるとしています。具体的には、以下の3つの要素が考慮されます。
- 指示・入力(プロンプト等)の分量・内容:詳細なプロンプトで具体的な指示を出しているか。
- 生成の試行回数:何度も試行して調整しているか。
- 複数の生成物からの選択:生成物の中から選んだり、手を加えたりしているか。
これらの要素が積み重なれば、生成AIで作った作品も著作物として保護される可能性が高まりますが、個別のケースごとに検討され、最終的には裁判で判断されることになります。
著作権以外にも、生成AIの活用には注意が必要です。生成AIで作成したコンテンツが他人の肖像権やプライバシーの権利を侵害するおそれや、フェイクニュースを拡散するリスクも指摘されています。ビジネスで利用する際は、こうした点にも配慮しましょう。また、社内の機密情報を生成AIに読み込ませることの可否は会社の方針に従いましょう。
なお、2024年7月、経産省から「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」が公表されました。このガイドブックでは、生成AIの活用事例や知的財産権に関する留意点、関係省庁のAIガイドラインの概要がまとめられています。ビジュアルが多く、読みやすい内容なので、ぜひご一読ください。

コンテンツ制作のための 生成 AI 利活用ガイドブック
ACCSは、生成AI時代を見据えて、AIと著作権に関する情報収集と発信を行っています。2024年度には、「AIと著作権」をテーマに、「生成AIと声」「生成AIとフェイクニュース」「生成AIと行政の取り組み」の3回のパネルディスカッションを開催しました。講演録やアーカイブ動画は、ACCSのwebサイトで公開しています。どなたでもご覧いただけます。
生成AIは、業務効率化やクリエイティビティ向上に役立つ一方、リスクも存在します。ACCSでは今後とも生成AIと著作権を中心に情報発信を続けてまいります。
活動報告
ACCS主催パネルディスカッション2024-2025「AIと著作権」
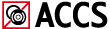
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)では、AIと著作権をメインテーマとして各界のステークホルダーにお集まりいただき、全3回のパネルディスカッションを開催いたしました。
生成AIは、誰もが手軽にクリエイティブな作品を生み出せる時代をもたらしました。 その一方で、生成AIによって作られたコンテンツは著作権法の枠を超え、様々な課題を生んでいます。ACCSでは、パネルディスカッションを通して、技術革新を妨げず、法とモラルをどのように協調させていくべきか、皆さんと共に理解を深めてまいります。
第3回「AI技術の進歩と"国として民間に期待すること"を理解~生成AIと行政の取り組み~」
(2025年3月17日開催)
第3回目は、生成AIと行政の取り組みをテーマとして開催いたしました。前半は、政府のAI戦略会議の検討状況や、AIと著作権に関する考え方、AIの利活用に向けた政府取組についての基調講演。後半のパネルディスカッションでは、民間での生成AIの利活用状況や課題を整理し、よりよい生成AIのあり方を探ります。
(Up&Coming '25 盛夏号掲載)



