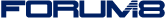vol.51
このコーナーでは、ユーザーの皆様に役立つような税務、会計、労務、法務などの総務情報を中心に取り上げ、専門家の方にわかりやすく紹介いただきます。今回は、日本におけるAI関連の法整備の現状と、AI新法の概要について解説いたします。
AI新法について
はじめに
人工知能(以下「AI」と略します)をめぐる海外の動きが非常に早く、日本でも追随する必要があるとされます。日本におけるAIに関する動きとしては主に著作権との関係を議論していたところ、生成AIが長足の進展を見せ、もはや一般の人々も巻き込まれる事態になってきています。
AIに関する最近の動きについては以下の通りです。
2023年5月 G7広島首脳コミュニケ[1]が公表
ガバナンス、知的財産権の保護、透明性の促進、外国の情報操作への対応、責任ある利用などを提唱
2023年5月AI戦略会議が「AIに関する暫定的な論点整理」[2]を公表
最近の技術の急激な変化や広島AIプロセスを踏まえて、AI戦略会議構成員がAI関連の論点を整理
2024年3月 文化審議会著作権分科会法制度小委員会が「AIと著作権に関する考え方について」[3]を公表
生成AIと著作権の関係について、適切なルール・ガイドラインの策定、共通理解の獲得、著作物のライセンス等の実施状況、
情報の共有などが図られることが、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から重要
2025年2月4日 知的財産戦略本部AI時代の知的財産権検討会が「中間とりまとめ」[4]を公表
2025年2月28日 内閣府よりAI法案[5]を国会に提出
2025年4月24日 衆議院で可決
2025年5月28日 参議院で可決
2025年6月4日 公布(法律番号53)
以下ではAI新法の礎である「中間とりまとめ」を概観した後、AI新法を概説します。
I.現状
2022年秋以降、生成AIの性能は飛躍的に向上し、国民生活の向上、国民経済の発展に大きく寄与する可能性があります。一方で、AIが使用される安全保障上のリスクも指摘されています。
国内外の状況として、EUでは包括的規制AI Actが発効し、米国では、コンテンツの透明性を高め、また使用データ開示について州法が制定され、日本では安全保障の観点で安全保障関係省庁を中心に別途検討が進行中です。
II.制度の基本的な考え方
- AIを特化型AI(特定のタスクを処理)と汎用型AI(様々なタスクを処理、生成AIが属す)に分類
- 関係主体として、AI開発者(データ収集やモデル学習その他の開発)、AI提供者(AIシステム提供又は組込みからサービス提供)およびAI利用者(サービスに組込み又は提供サービスを利用)とする(他に国外事業者も検討)
- イノベーション促進とリスクへの対応の両立
AIについては、様々なリスクを生じさせうる一方で、国民生活の向上、国民経済の発展に大きく寄与する可能性があり、AIのイノベーションの促進とリスクへの対応を両立させることが重要 - 広島AIプロセスの考え方に基づき議論をリードし、モデルとなるようなAI制度を発信すべき
III.具体的な制度・施策の方向性
全体を俯瞰する政府の司令塔機能の強化、戦略の策定、また、安全性の向上のため、透明性や適正性の確保等が求められており、必要に応じて制度整備することが適当。
(国会に提出された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」[5])
AI新法の必要性として日本のAI開発・活用が遅れているとの認識の一方で、多くの国民がAIに対して不安を抱いているという現状があるとされます。このため、イノベーション促進とリスク対応のため既存法律に加えて新法が必要とされます。以下では、AI新法についてその概略を紹介します。法律の文言はその意味の理解が難しいため、多少の誤解を恐れずかみ砕いた記載としています。詳しく確認したいときは出典を参照ください。
目的と定義
(目的)第一条
国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与する
※本法律の目的を規定しています。法律の目的に沿って種々の実施等について解釈されると考えられます。
(定義)第二条
「人工知能関連技術」の定義
特許法では発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、さらに発明の実施行為を定義しています。これらの定義により、権利者と第三者との調整をより円滑にしています。
AI新法では人工知能関連技術の定義はあるものの、より具体的な実施行為などの定義は明確ではありません。これは法趣旨から著作権法、不競法など他の法律により調整されることになると考えられます。
基本理念
(基本理念)第三条
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進は、基本理念に基づいて行う
AI戦略本部
本部組織(第二十一条)は、人工知能戦略本部長(第二十二条;内閣総理大臣)、人工知能戦略副本部長(第二十三条;内閣官房長官及び担当大臣)及び人工知能戦略本部員(第二十四条;国務大臣)により構成される
その他、資料の提出その他の協力(第二十五条)、事務(第二十六条)、主任の大臣(第二十七条)および政令への委任(第二十八条;必要事項は政令で定める)を規定
AI基本計画
(人工知能基本計画)第十八条
基本的施策
国は以下の施策を講じる
責務
(国の責務)第四条
(地方公共団体の責務)第五条
(研究開発機関の責務等)第六条
(活用事業者の責務)第七条
(国民の責務)第八条
(施行期日)公布の日から、第三章及び第四章、附則第三条及び第四条の規定は政令で定める日から施行する
(検討)政府は、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる
出典
[1]G7広島首脳コミュニケ
https://www.mofa.go.jp/files/100507035.pdf
[2]AIに関する暫定的な論点整理
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ronten_honbun.pdf
[3]AIと著作権に関する考え方について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
[4]中間とりまとめ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000992019.pdf
[5]AI法案
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217anbun_2.pdf
監修:弁理士法人相原国際知財事務所
(Up&Coming '25 盛夏号掲載)